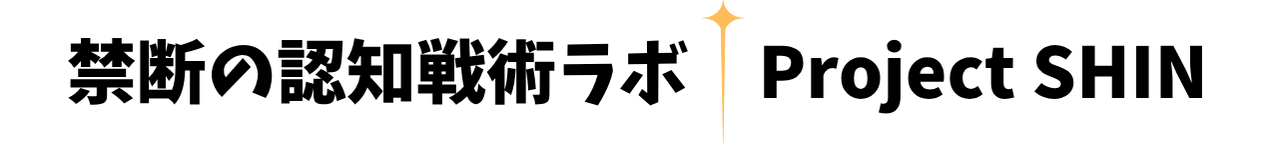言葉があなたをつくっている
「頑張る」「普通」「ちゃんと」——
この言葉たちは、私たちを励ますようでいて、同時に縛る言葉でもあります。
私たちは言葉を“使っている”と思っていますが、
実際には言葉のほうが、私たちを使っているのかもしれません。
文部科学省の調査によると、日本語話者の約8割が
「自分の考えを言葉で表すのが苦手」と答えています。
さらに国立国語研究所のデータでは、SNSで使われる上位100語のうち70語が
「やばい」「最高」「無理」といった感情テンプレートでした。
つまり、私たちは“自分の言葉”で考えているようで、
実は社会が設計した言葉を“使わされている”のです。
誰があなたの言葉を設計したのか
文化庁の「日本語のゆくえ」調査では、
過去10年間にメディアで最も頻出した言葉の上位が
「努力」「我慢」「絆」「安心」「挑戦」。
これらの言葉は、どれも“良いこと”のように見えます。
でも実際には、社会が秩序を保つために生み出した「感情コード」でもあります。
心理言語学では、言葉が思考を制御する現象を
サピア=ウォーフ仮説と呼びます。
私たちは言葉の枠の中で現実を見ています。
たとえば、「忙しい」が口癖の人は、
常に“タスクを探す脳”で日々を過ごしています。
逆に「充実している」と言い換える人は、
同じ行動量でも幸福感を感じやすくなる。
言葉を変えるだけで、
現実の意味づけが変わるのです。
沈黙から始まる「自分の言葉」
自分の言葉を取り戻す最初の一歩は、
“沈黙を恐れないこと”です。
沈黙には、まだ名前を持たない思考の芽が隠れています。
誰かの反応を先読みして安全な言葉を選ぶのではなく、
自分の中に“しっくりくる言葉”が見つかるまで、
少し待ってみるのです。
“頑張る”をやめて、“工夫する”と置き換える。
“我慢する”をやめて、“選ぶ”と書き換える。
小さな言い換えが、思考の方向を変えていきます。
半年もすれば、
あなたが使う言葉は少しずつ変わっているはずです。
それはつまり、自分の世界を再設計しているということ。
あなたの「言葉OS」を書き換える3つのワーク
ここからは、読者のあなたが実際に“自分の言葉OS”を更新するための
3つのワークを紹介します。
どれも「ノートとスマホだけ」でできる、簡単な実践です。
ワーク1|自分の口癖を“見える化”する
1日だけ、自分の発言をスマホのメモに残してみましょう。
家族との会話、仕事のチャット、SNS投稿……どんな言葉でもOKです。
夜になったら、その中から「よく出てくる言葉ベスト5」を選びます。
例:
- 「すみません」
- 「まあいっか」
- 「忙しい」
- 「頑張ります」
- 「大丈夫です」
次に、その言葉が「誰のための言葉」か考えます。
- 「すみません」→相手に気を使うため
- 「忙しい」→自分を正当化するため
この時点で、自分の“言葉の支配構造”が見え始めます。
自分の言葉なのに、実は他人のために使っているものが多いことに気づくはずです。
ワーク2|言葉の“再定義カード”を作る
ワーク1で見つけた言葉をひとつ選び、
それを自分の定義で書き換えるカードを作ります。
例:
- Before:「頑張る=我慢して続ける」
- After:「頑張る=工夫して進む」
- Before:「ちゃんとする=周りに合わせる」
- After:「ちゃんとする=自分に誠実である」
書いたカードをスマホの待ち受けやデスクに貼り、
1日3回、声に出して読み上げてください。
言葉を声にすることで、脳の神経回路が少しずつ再配線されていきます。
ワーク3|“言葉の棚卸しノート”で更新履歴を残す
ノートを開き、ページを左右2列に分けます。
左側には「これからも使いたい言葉」、
右側には「もう使いたくない言葉」を書き出します。
例:
| 使いたい言葉 | 使いたくない言葉 |
|---|---|
| 探求する | 我慢する |
| 試してみる | 失敗したくない |
| 面白い | 忙しい |
| 一緒にやろう | 無理だよ |
書き出したら、各言葉の横に「理由」を書きましょう。
たとえば:
- 「探求する」→ワクワクがある
- 「我慢する」→体も心も固まる
こうして月に一度ノートを見返すと、
自分の中でどんな価値観がアップデートされたかが一目で分かります。
それは、あなた自身の“思考の履歴書”になるのです。
言葉を変えると、世界が変わる
誰かの台本を降り、自分の定義で語るとき、
あなたの世界は新しいバージョンへとアップデートされます。
言葉を取り戻すことは、
あなた自身の人生のソースコードを取り戻すことなのです。
出典・参考
- 文部科学省「国語教育の現状と課題」(2024)
- 国立国語研究所「現代日本語語彙頻度調査」(2023)
- 文化庁「日本語のゆくえ」(2023)
- OECD「成人スキル調査(PIAAC)」(2022)
- 日本心理学会紀要「言語と思考の相互依存」(2023)