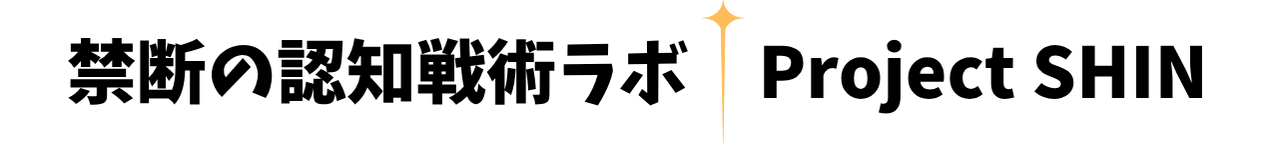脳は「覚えないように」できている
「覚えられない」「すぐ忘れる」「勉強しても定着しない」。
多くの人がそう感じていますが、まず伝えたいのはこれです。
あなたの脳は、覚えないように設計されている。
驚くかもしれませんが、これは怠けでも老化でもなく、
生物としての正しい防衛機能なのです。
人間の脳は1日に数千〜数万件の情報を受け取ります。
そのすべてを覚えていたら、思考はすぐに破綻します。
そこで脳は、重要度の低い情報を自動で削除する仕組みを持っています。
心理学者ヘルマン・エビングハウスが示した「忘却曲線(1885)」は有名ですが、
現代の脳科学でも、“忘れること”は効率的な記憶維持の戦略であることが確認されています(Richards & Frankland, 2017, Neuron)。
つまり、「覚えられない脳」は、むしろ“情報の交通整理が上手い脳”なんです。
覚えられない理由を「構造」で見る
「覚える力」よりも大切なのは、「記憶の構造」を理解することです。
脳科学的に、記憶は3段階で処理されます。
- 入力(encoding):情報を感覚から取り入れる
- 保存(storage):脳内に一時的に格納する
- 想起(retrieval):必要な時に引き出す
この3つのどこかで「つまずき」が起きると、記憶は定着しません。
特に現代人の多くが失敗しているのは、2. 保存の段階で環境が邪魔をしている点です。
通知、SNS、マルチタスク、雑音——
脳が「一時保存モード」のまま切り替わらず、長期記憶へ送る処理をする時間が取れない。
つまり、「覚えられない」は意志ではなく設計のバグです。
「忘れにくい環境」を設計する
脳は環境に非常に影響を受けます。
特に「どこで」「どの状態で」学ぶかが、記憶の強度に直結します。
たとえば、
- 同じ時間・同じ場所で学ぶ
- 同じBGMをかける
- 学んだ内容を同じフォントや手書きで整理する
などの工夫は、脳に「再現の手がかり」を植え付ける設計です。
記憶力を高めるとは、“脳が再現しやすい環境”をつくることなのです。
忘れにくい脳を育てる3つの実践ワーク
ワーク1|「10秒再現メモ」実験
今すぐ、10秒だけで読める短文をひとつ選んでください。
たとえばニュースの見出し、メールの一文、カフェのメニューなど。
それを読んで、メモ帳を閉じ、30秒後に「その内容をできるだけ正確に再現」してみましょう。
たいていの人は、3割も正確に思い出せません。
でもこれでいいんです。
この体験をきっかけに、あなたは「記憶力=再現設計力」という感覚を掴み始めます。
そしてこれが、後のワーク2・3の基盤になります。
ワーク2|「五感でつなぐ」学びの定着化
私たちは、覚えるときよりも「思い出す場所」がバラバラです。
だから、脳がどこで何を引き出せばいいか混乱します。
今日から、ひとつだけ“思い出す場所”を決めてください。
たとえば——
- 朝、コーヒーを飲む席で「昨日の学びを3つ思い出す」
- 通勤電車の中で「昨日のメモを1つだけ読み返す」
- 夜、歯磨き中に「今日覚えたことを1文で口に出す」
どれでも構いません。
場所 × タイミング を固定するだけで、
脳は「ここ=思い出す場所」と認識し、再現率が上がります。
1週間続けると、不思議なことに、
その場所に座った瞬間、思考が自動的に“復習モード”に切り替わるようになります。
🪄 コツ:頑張らず、思い出すための“きっかけ”を置く
- コーヒーのカップ横に小さなメモを置く
- 歯磨きの棚に「思い出す」と書いたポストイットを貼る
- 通勤中、リマインダー通知に「昨日の3つ」と出す
これで環境そのものが、あなたの外部トリガー(再現スイッチ)になります。
覚えるより、思い出す場所を決める。
それだけで、脳は“呼び出す設計”に切り替わります。
ワーク3|「外部脳ノート」で“記憶の倉庫”を作る
人間の脳は、情報を覚えておくのが苦手です。
でも「どこに書いたか」を覚えるのは得意。
この性質を利用して、外部に記憶を置く仕組みをつくります。
用意するのは、ノート1冊だけ。
デジタルでも紙でもOKです。
ルールは3つ。
ノートを1冊決める。
なんでもいいです。お気に入りのメモ帳でも、スマホのメモでもOK。
思いついたことを、すぐ書く。
整理不要。「あとでまとめよう」と思うと忘れるので、
“投げ入れノート”として何でも放り込みます。
週に1回、パラパラ眺める。
覚え直す必要はありません。
ただ見るだけで、「忘れた情報」が再び脳に呼び戻されます。
ノートの目的は「記録」ではなく「再会」。 見返すときに“思い出せた”体験を作ることが、記憶を固定します。 続けていくと、脳が「ここにある」と信頼し、安心して忘れられるようになります。
この「再現リスト」は“過去に書いたけど忘れていた知識”を再起動させる役割を果たします。
脳科学的には、これが再固定化(reconsolidation)を促す行動です。
書くことより、“書いたものに再び出会う”ことが、記憶を永続化します。人間の記憶は不安定ですが、
外部環境を上手に使えば、拡張記憶として機能します。
→ 覚える努力をやめて、“思い出す場所”を持とう。
それが、あなたの外部脳です。
記憶力は努力ではなく、設計力
覚えられない自分を責める必要はありません。
それは怠けではなく、脳が効率を優先している証拠です。
大切なのは、「もっと頑張る」ではなく、
「覚えやすく、忘れにくい環境を設計する」こと。
努力を設計に変えた瞬間、記憶はあなたの味方になります。
📚 出典・参考
- Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis.
- Richards, B. & Frankland, P. (2017). The Persistence and Transience of Memory, Neuron.
- Smith, S.M., & Vela, E. (2001). Context-dependent memory in the real world.
- 厚生労働省「生活時間と学習行動調査」(2023)