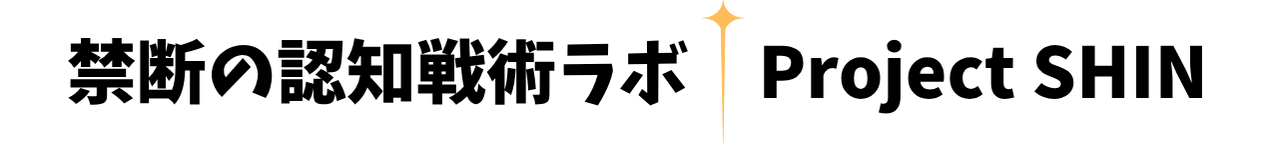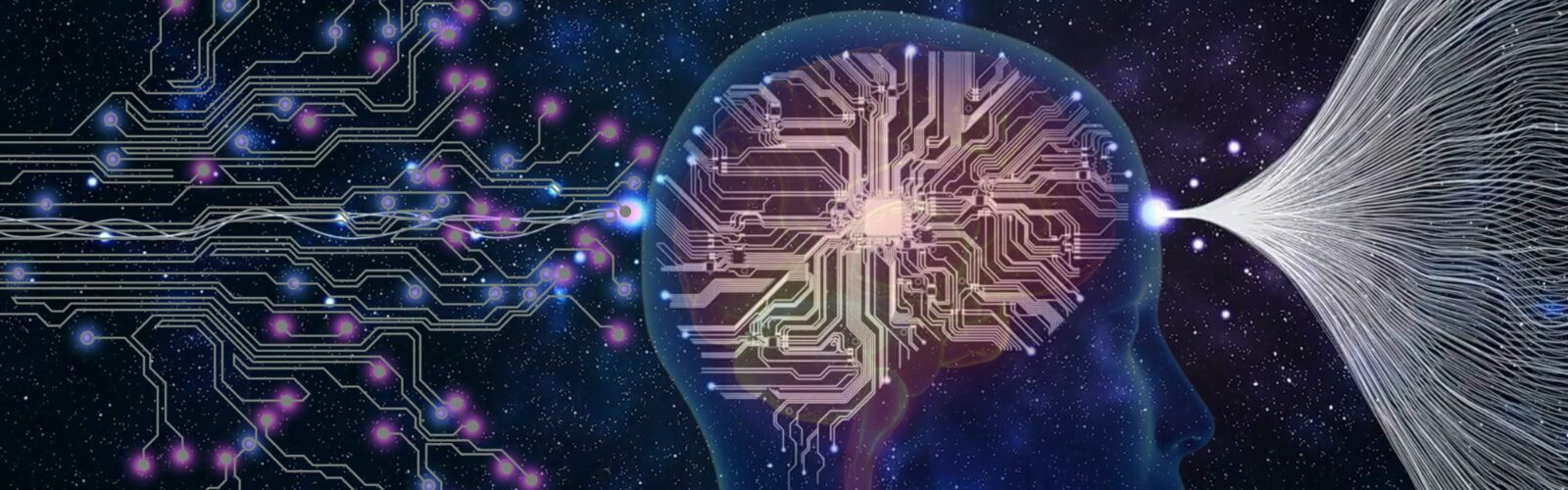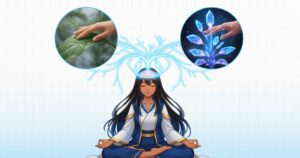🎬 この記事の約8分解説動画です。本文と合わせてどうぞ。
「気が合う」「気が重い」「気を抜く」。
私たちは日常的に「気」という言葉を使っていますが、
その正体を明確に説明できる人は少ないのではないでしょうか。
「気」は確かに感じられるのに、
現代科学ではまだ完全に説明できていません。
それでも、「気が存在しない」とは言い切れない。
なぜなら、気は情報だからです。
「気」は情報そのもの
「気は実在しないが存在する」。
この言葉は一見、矛盾して聞こえます。
しかし、情報という観点で見れば理屈が通ります。
たとえば「空気」は目に見えませんが、
私たちはそれが確かに“ある”と知っています。
気もそれと同じように、見えないが確かに作用する情報の流れなのです。
気は「何か不思議な力」ではなく、
人と人、心と体、意識と無意識を結ぶ情報媒体として考えると理解しやすくなります。
だからこそ、「気」はオカルトではなく、実用的に扱う対象なのです。

科学者の立場から見た「気」
科学者の視点から見ると、
気の正体はまだ完全に解明されていません。
磁場の変化なのか、微弱な電磁波なのか、あるいは量子レベルの相互作用なのか——
現代の物理学や脳科学では、その本質を測定しきれないのです。
しかし、臨床や観察の現場では、
“言葉を超えた伝達”が確かに起きていることが認識されています。
医療現場の気功研究や、心理・音響分野の研究者たちは、
「気」を情報場(information field)として捉えようとしています。
つまり、科学が追いついていないだけで、
人間同士の“情報共鳴”という現象は確かにある。
それを解明するための言語と測定技術が、まだ整っていないだけなのです。
人間と情報の伝達
人間は、言葉というツールを使って脳の意志を伝達します。
しかし、それだけでは説明できない“伝わり方”があります。
たとえば、言葉にせずとも相手の感情がわかる。
相手が怒っているか、悲しんでいるかを、
声や表情よりも先に感じ取ることがある。
その伝達経路は、
・磁場の微細な変化なのか
・電磁波としての共鳴なのか
・あるいは量子的な通信なのか
まだ断定できません。
けれど確かなのは、
「情報」は言語以外の経路でも伝わっているということです。
これを古来の人々は「気の交流」と呼び、
現代では「非言語的コミュニケーション」や「情報場の共鳴」と呼び始めています。

気功の現場に見る「情報場の共有」
実際の医療気功の現場では、興味深い現象が観察されます。
気功師が「頑張りなさい」と声をかけなくても、
患者はそのメッセージを受け取ります。
治るための「気」が、その場全体に流れているのです。
気功師は患者の体を直接操作するのではなく、
“治るための情報”を共有する空間をつくるのです。
患者はその情報を無意識に受け取り、
自分自身の内部表現を通して「治る方向」へと変化していきます。
このとき、両者の間には「気の空間」が生まれます。
言葉を交わさずとも、
信念・意志・集中が情報として伝達される空間です。
それは物理的な接触ではなく、
共有された情報場でのやり取りなのです。

「気」を実利で考える
「気は実在しないが存在する」。
つまり、目で見ることはできなくても、確かに作用する。
であれば、それをどう活かすかを考える方が建設的です。
気は、心の状態や集中力、他者との関係性を左右する情報の質です。
たとえば、
・プレゼン前に「気を整える」ことで声が安定する。
・人と会う前に「気を澄ます」と、相手に安心感を与えられる。
・呼吸を整えるだけで、心のノイズが減り、思考が明晰になる。
このように、気を“情報の調整技術”として捉えると、
日常生活や仕事のパフォーマンスを高めることができます。
1分ワーク:情報としての「気」を感じる
- 静かな場所で、背筋を伸ばして座ります。
- 鼻からゆっくり息を吸い、3秒止めて、7秒かけて吐きます。
- 手のひらを胸の前で向かい合わせにし、10センチほど離します。
- その間に「空気の厚み」や「温度の変化」を感じてみてください。
感じた微妙な変化こそが、あなたの情報場の感度です。
それを感じ取る力を育てることで、
言葉を超えた伝達の精度が高まっていきます。
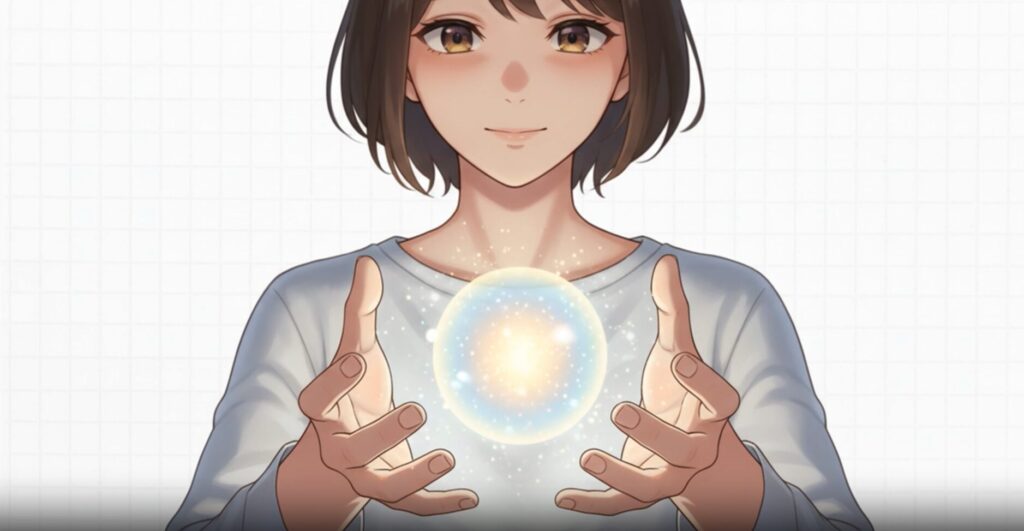
結び——「気」を科学と実践のあいだで捉える
気を不思議なものとして切り離すのではなく、
情報として理解し、実生活に活かすことが大切です。
科学はまだその全容を説明していませんが、
感じ、使い、共有することは誰にでもできます。
それは目に見えないけれど確かにある——
私たちをつなぐ、**情報としての“気”**なのです。